 ○物が見えるしくみ
○物が見えるしくみ症状等でご心配な点がございましたらご自分で判断されずにお医者さんへご相談ください。
カメラでは、被写体の像はレンズを通して、フィルムに到達します。その際、レンズを前後に移動させてピントを合わせたり、また絞りで光の量を加減することにより、被写体の像がフィルムにはっきりと写るように調節します。
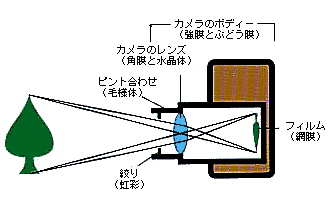
目に入ってきた光は、角膜と水晶体を通り屈折して、網膜に像が写し出されます。目はピントを合わせるために、毛様体(もうようたい)により水晶体の厚さを調節しています。また、虹彩(こうさい)により光の量も加減します。
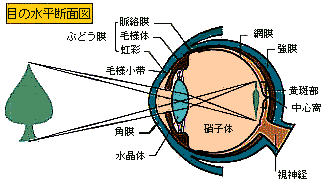
フィルム上に写る像も網膜に写る像も上下左右が逆さまになっています。フイルムの場合は反転させることにより正しい方向にします。目の場合は脳が逆さまになった像を正常とみなすように慣らされているので、正しい方向で見えるように感じます。
 -先頭へ-
-先頭へ-
正視では、近いところを見るときは点線のように水晶体がふくらみ、網膜にピントが合います。
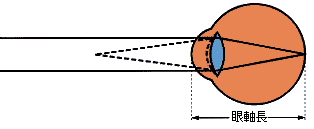
眼軸の長さが長すぎると、遠くを見たときに水晶体を十分薄くしても、網膜上でピントが合いません。網膜の手前でピントが合ってしまいます。このような近視を軸性近視(じくせいきんし)と呼びます。大部分の近視は軸性近視です。
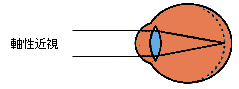
角膜・水晶体の屈折力が強すぎると、遠くを見たときに網膜上でピントが合いません。網膜の手前でピントが合ってしまいます。このような近視を屈折性近視(くっせつせいきんし)と呼びます。
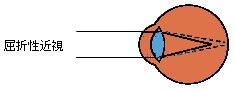
 -先頭へ-
-先頭へ-
眼軸の長さは、成長に伴い伸びていきます。新生児は眼軸の長さが短く、たいてい遠視の状態になっていますが、角膜・水晶体の屈折力が強くなっているので、それほどひどくはありません。角膜・水晶体の屈折力は、眼軸の長さが伸びるとともに弱くなり、全体のバランスが調整されるようになります。しかし、環境の影響などでこれらのバランスが崩れると、近視になると考えられています。
*遠視とは、網膜の後方でピントが合うため、遠くを見るときはもちろん、近くを見るときも調節しないとはっきり見えない目のことです。
親が近視の場合、子供が近視になる可能性は比較的高く、遺伝的な要素が複雑にからんでいると考えられます。
一般的な近視の場合、環境も影響すると考えられています。勉強、読書、テレビ、コンピューターゲームといった近くを見る作業を長く続けていると、目が疲れ、好ましくないのはいうまでもありません。しかし、こういったことが近視の原因になるかどうか、はっきりした証明はありません。
 -先頭へ-
-先頭へ-
遺伝や環境の影響などにより、小学校高学年〜中学校くらいで始まる近視を単純近視といいます。病気というより身長や体重と同じ個人差です。在学中に発生することが多いので学校近視ともいわれ、大部分の近視は単純近視です。
ごく一部の近視は、幼児期の段階から始まり進行します。眼軸が異常に長くて近視の度が強いため、眼鏡をかけてもあまりよく見えるようにはなりません。また、眼球がかなり大きくなっているため、網膜が引き伸ばされて非常に薄くなっており、目をちょっと打っただけで、網膜の中心部がひび割れや出血によって萎縮したり、網膜が眼底から剥がれてくる「網膜剥離(もうまくはくり)」などの症状を起こします。このような近視は病的近視と呼ばれ、発生する原因がまだ不明で、遺伝が関与しているともいわれます。矯正しても幼児が、遠くも近くも見にくくしているようであれば、注意が必要です。
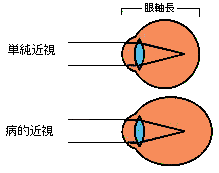
 -先頭へ-
-先頭へ-
近視の矯正には凹レンズを使います。凹レンズは焦点(ピントが合う点)を遠くにする働きがあり、近視の人が適切な度の凹レンズをかけると、網膜にピントが合って遠くがよく見えるようになります。
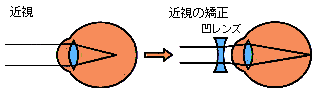
近視になったからといって、日常生活に支障を来さなければ、すぐに眼鏡をかけなければならないということはありません。黒板の字が見えにくくなるというような不都合が生じてきたら眼鏡をかけてください。 また、眼鏡を常にかける必要はなく、黒板や遠くを見るときなど必要に応じてかければよいのです。眼鏡をかけたりはずしたりしても、近視の度が進むようなことはありません。
 コンタクトレンズは角膜の表面に接触させて用いるレンズで、目立たないことから眼鏡をかけたくない人に好まれています。左右の視力に差がありすぎて眼鏡が使えない場合でも矯正でき、眼鏡のように曇ったりせず、視野が広くなるという優れた点があります。しかし、慣れるまでに時間がかかる、異物感がある、角膜を傷つける場合があるといった欠点のため、使用するときは眼科の先生と相談の上、決めましょう。また、レンズの取り扱いや管理などが大変なので、小学生の間は眼鏡をかけることをおすすめします。
コンタクトレンズは角膜の表面に接触させて用いるレンズで、目立たないことから眼鏡をかけたくない人に好まれています。左右の視力に差がありすぎて眼鏡が使えない場合でも矯正でき、眼鏡のように曇ったりせず、視野が広くなるという優れた点があります。しかし、慣れるまでに時間がかかる、異物感がある、角膜を傷つける場合があるといった欠点のため、使用するときは眼科の先生と相談の上、決めましょう。また、レンズの取り扱いや管理などが大変なので、小学生の間は眼鏡をかけることをおすすめします。
 -先頭へ-
-先頭へ-
点眼薬を用いる治療法は、近視になりかけの偽近視(仮性近視)の時期に行われることがあります。偽近視は近くを長く見続けた結果、毛様体節が異常に緊張して水晶体が厚くなり、一時的に近視の状態になっていると考えられるときで、目の調節を休ませる点眼薬を用いる場合もあります。手術的方法には、角膜周辺部分を放射状に切開する「放射状角膜切開術」やエキシマレーザーによる「角膜切除術」(角膜の中心部分を削る方法)などがあります。 しかし、強度の近視では効果が弱く、また、安定した視力が得られない場合や後遺症が残る場合もあり、効果と安全性が現在検討されています。治療を受ける場合は、十分説明を聞いて納得してから受けましょう。
病的近視は、現在のところ有効な治療方法がなく、研究が続けられています。網膜剥離や眼底出血などが起こらないように注意し、起きた場合は早急に手術する必要があります。
 -先頭へ-
-先頭へ-
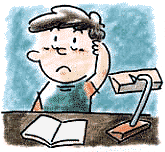
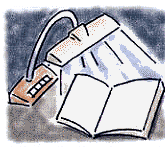



 -先頭へ-
-先頭へ-
大部分の近視は病気ではなく、遠くが見えにくいだけのふつうの目です。現代社会では近くを見る作業の方が多いため、近くがよく見える近視の方が有利な場合もあります。日頃から目をいたわる生活を心がけ、見えにくくなってきたら眼科の先生に相談してみましょう。また、度が進まないようでも目を守るために、1年に1回は検眼してもらいましょう。
 -先頭へ-
-先頭へ-